ロシアを始めとした世界各地で開催される国際音楽祭に度々招かれるなど、世界を舞台に活躍されていらっしゃる音楽家・作曲家の浅香満さんのコラム「ロシア音楽裏話」第12話です。
前回までの連載記事はこちらから
(以下、浅香さんのコラムです)
.
.
.
.
.
学生時代に世界的作曲家であるT・M先生の「管弦楽法」のクラスで多くの薫陶を受けたことが、単に楽器の使用方法に留まらず、先輩諸氏とのあたたかい関係を構築することに繋がり、この延長線上にこの度のロシア、タタールスタンでの国際音楽祭の舞台が用意されていることに不思議な「ご縁」を感じると共に、かかわってくださった方々のご配慮、ご尽力には未だにいくら感謝しても足りるものではありません。
その「管弦楽法」で、当時まだ一度も自身の書いた楽譜がオーケストラで演奏されたことの無い私のような「超初心者」が「手っ取り早く」且つ「効率よく」且つ「効果的に」楽器法の技術を習得させるためにT・M先生が考えてくださったことが、「超初心者」が書いた楽譜を「曲者」「偏屈」「難癖」「マフィア」というキーワードがマッチする日本一、否、世界一「厄介」と称される大学管弦楽研究部(大学教員によるオーケストラ)に実際に演奏させることでした。
このオーケストラは学生たちに音楽業界の厳しさを教え込むことを何よりの使命・・・というか楽しみにしており、通常ではまず起こり得ない様々なトラブルについても「デビューする前」に体験させておくべきという方針があるようで、共演が決まった学生は皆、戦々恐々としておりました。
何やら若きラフマニノフ(以前にもお話いたしましたように「タタール人」の血が流れています)の最初の交響曲の初演時のエピソードが想起されます。
元々、少年時代のラフマニノフはペテルブルク音楽院に在籍していたのですが、のちに歴史に名を残すことになるのが信じ難い素行不良、成績不振(ちゃんと通学していなかったようです)により半ば強制的に退学させられてしまいます。
しかし、モスクワに移って鬼教師、「野獣」の異名をとるニコライ・ズヴェレフ(ズヴェーリ=野獣と言う意味で、同性愛者であり特に「少年」が大好きでした。このズヴェレフの指導によって「才能を開花」させた少年も数多くいましたが、同時に「破滅」させられた者も少なくなかったようです)のピアノの猛特訓によって「才能を開花」させ、遂にはモスクワ音楽院でピアノ科のみならず作曲科の両方で金賞を獲得(二つの部門で金賞を得ると「大金賞」)します。
しかし、次期音楽学院長の椅子を虎視眈々と狙うサフォーノフ教授と自分の師匠であるジロティ(ラフマニノフにとっては従兄でありズヴェレフの兄弟子、この従兄からズヴェレフを紹介されています。
因みにジロティは同じく同性愛者であったチャイコフスキーの「男性の愛人」であったという説もあります)の確執に阻まれて野心作である最初の交響曲がモスクワで初演できず、「二大都市」のもう一つであるぺテルブルクで初演せざるを得ない(若手の駆け出し作曲家にとってはどこで初演されるのかが重要で、名も無い地方都市では「箔」が付かないため)状況に追い込まれてしまいます。
かつてペテルブルク音楽院が見切りを付け、才能無しという烙印を押した若者に「凱旋」されるとメンツが立たなくなってしまうため、「意図的」に失敗させられてしまうのです。
初演の指揮者、グラズノフはただでさえ「大酒飲み」(ロシアでは「大酒飲み」はスタンダードであるといえましょう)であったのですが、コンサート本番直前にもかかわらずいつもより「余計」に酒を浴びるように飲み、指揮台に千鳥足で向かったと伝えられています。
この初演は散々で辛口批評家、毒舌評論家として知られているツェザール・キュイ(いわゆる「ロシア五人組」の作曲家の一人、カザンで学生時代を過ごしたバラキレフが「五人組」のリーダーであり、最初はこの二人で活動を開始しました。
後にムソルグスキー、リムスキー=コルサコフ、ボロディンの順にメンバーが加わります。
なお、「ロシア五人組」という言い方は専ら海外からの呼称で、ロシア本国では「マグチカヤ・クーチカ」即ち「強力な一団」と呼ばれています)は「もし地獄に作曲コンクールがあったとすれば、ラフマニノフの交響曲は間違いなく1等賞である」と辛らつな言葉で酷評しています。
なお、キュイはこの他にも至る所で散々毒を吐いていながら肝心の自身の作曲の方面では音楽史上に燦然と輝くような名作を全く残すことができず、その論争好きで気難しい人間性も災いしてかペテルブルクのアレクサンドル・ネフスキー寺院に眠る彼の墓はごく質素な「十字架」のみ(先祖はもともとフランス人で、ナポレオンの率いる軍隊に従軍してロシアに入ったため「ロシア正教」ではなくカトリック教徒でした)となっており、一緒にこの墓地に眠るバラキレフの風格のある重厚な墓、リムスキー=コルサコフの洒落た墓、ムソルグスキーの胸像を施した立派な墓、ボロディンの金箔の楽譜(代表作である歌劇「イーゴリ公」のダッタン人の踊りの冒頭の旋律です。音楽史上に残る作曲家としては極めて珍しい完璧な「人格者」であり、音楽の他にも医学、化学でも功績を残しただけでなく女性の高等教育への道も開き、幅広い分野で多くの人々の尊敬を集めていました。彼の心「=生み出した旋律」は最高「=金」であることを象徴しています)に彩られた美しい墓と鋭く対照をなし、ある意味、「印象的」でもあります。
因みにキュイの隣は彼等「五人組」の倍以上の規模を誇るこの墓地で一際豪華で威厳に満ちたチャイコフスキーの墓が鎮座しています。キュイの墓が、金箔に輝く「最も美しい」ボロディンと「最も豪華」なチャイコフスキーに挟まれるように配置されているところに、生前キュイに苦しめられたであろう大勢の音楽関係者の怨念、悪意が「当てつけ」のように反映されていると感じてしまうのは私だけでしょうか・・・
さて、そのラフマニノフの交響曲初演の「歴史的」失敗の「元凶」は指揮者のグラズノフの筈なのですが、批判の矛先が彼に向かうことはありませんでした。
何故ならグラズノフの師匠は「五人組」の重鎮、リムスキー=コルサコフであり、当時、ペテルブルク音楽院の学院長という要職にありましたので、弟子であるグラズノフを批判することは音楽界の最高権力者でもある音楽院学院長の顔に泥を塗ることに繋がり、もしこの学院長に睨まれてしまうとこの地での音楽活動、評論活動が難しくなってしまうことを意味し、何よりペテルブルクの音楽界全体が件の理由でラフマニノフの成功を全く望んでいなかったことが挙げられます。
この出来事ですっかり自信を喪失したラフマニノフは、以後、3年にわたって作曲ができなくなってしまったことは有名な話です。
精神科医、ニコライ・ダール博士の暗示療法で復活するのが定説(この説に否定的な考えもあります)ですが、少なくともこの期間にラフマニノフは自分の音楽活動、作曲に対する姿勢を真摯に見直したといえます。
それは学生時代に作曲したピアノ協奏曲「第1番」の出だしが自らのピアノ演奏テクニックをひけらかすような眩いばかりの超絶技巧に彩られているのに対し、復活後の最初の作品であるピアノ協奏曲「第2番」の冒頭は静かに響くロシア正教の「鐘」で幕を開けています。
ラフマニノフの生まれ育ったノブゴロドは「歌と鐘の街」としてしられ、幼少時代を「鐘」の響く中で過ごし、鐘撞職人とも交流があったことが自らの音楽の「原点」にあることを認識し、虚飾を排した作曲の姿勢が如実にこの復活作品に反映されています。
結果的にこの作品は彼の最高傑作と位置付けられ、作曲家として揺るぎない地位を固めることになり、交響曲の初演に失敗したことこそが、これまでに気付かなかった彼自身の音楽に内在する本質を問い直すことになりました。
話を「難癖オーケストラ」に戻しますと、学生が共演する際、何と演奏する「前」から、例えばステージ中央に向かって歩くスピード、姿勢、お辞儀の角度等の一つ一つに細かい「指導」が入り、団員の迫力に圧倒されて委縮しようものなら「そんな音じゃ、聴衆の心に響かない」「そんな演奏ではオーケストラとは共演できない」少しでもミスをしようものなら「お前はナめとるのか!」と言った罵声が飛び交います。
更にここには書くことが憚られる、良識のある人なら眉を顰めそうな、もし当時SNSがあれば間違いなく炎上しそうなことも多々ありました。
この「試練」「洗礼」に耐えて実際に国際舞台に羽ばたいた逞しい輩もいますが、すっかり怖気付いて「引きこもり」状態に陥ってしまう者も珍しくありませんでした。
いつの世もラフマニノフとズヴェレフのように「過激で癖の強い指導」は大いに「才能を開花」させる可能性を秘めているのと同時に、本来備わっていたかもしれない才能を「破滅」させてしまう「諸刃の剣」であるといえそうです。
私はこの「難癖オーケストラ」そのものには初対面でしたが、団員のお一人を存じ上げており、この方には実はちょっと「顔向け」できない事情がありました。
高校時代、私は吹奏楽部に所属していたのですが、この部活を指導してくださったのが何を隠そう、このオーケストラの団員、しかもトランペットセクションのトップ(一番偉い方)を務めているY・O先生でした。
先生は無類の車好きで、当時、国産最速のパワーを誇るド派手なスポーツカーで学校に乗り付け、その車が到着すると生徒は勿論、教職員から警備員までもが群がる光景がよく見られました。(「最速」でしたので警察も高速道路での取り締まりに使用していた車種で、この車に追跡されると外国の高級、高性能車でも簡単に逃れることができませんでした)
お察しの通り先生は「スピード狂」であり、この車の性能を一般道路でも遺憾なく発揮されていました。
結果的に「スピード違反」で頻繁に警察に捕まっていたのですが、全く意に介する様子はありませんでした。
先生曰く、「人間は何故、飛行機を発明したのか? 何故、新幹線を開発するのか? できるだけ速やかに移動したいと願うのが人間の本能である」と高校生の我々に熱く語り、「スピード違反」の「罰金」は「必要経費」であると豪語されておりました。
さすが、難癖オーケストラのトップです。
しかし、毎回来校される度に披露されていたこの持論がいつかパタッと止んだことがありました。
なんでも「同じ日」に「2度」スピード違反で検挙され、ついにその場で即「免許停止」を言い渡されてしまったそうで、以後しばらくは路線バスで来校されていました。
さて、そのY・O先生が車の話と共に口癖のように語っておられたのが「自分の指導するバンドから音楽の専門家を出したくない」ということでした。
先生のご経験から音楽との最も理想的な付き合い方、心から音楽を楽しむためには「それを職業としない」ことであるという結論に達したそうです。
よって、音楽大学に入学してしまった私は謂わば「不肖の」生徒と言えそうで、ご挨拶にお伺いしたいと思いつつ、管弦楽研究部は「マフィアの巣窟」とも揶揄されていることもあってなかなかそこのドアをノックすることができませんでした。
しかし、皮肉なことに音楽を演奏する喜びはそのY・O先生のご指導を通じて感得したのでした。
部活の夏合宿は例年、尾瀬片品村で実施されていました。
水芭蕉の名所として知られているこの地はゆったりとした心落ち着く時が流れ、都会の喧騒から離れて実り多い成果を上げることができるのでした。
合奏の練習場として夏休み中の地元の小学校の体育館をお借りしていたのですが、合宿後半に差し掛かるところで校長先生が我々の宿舎を訪問されました。
この地ではなかなか「生」で音楽を聴く機会が少ないので、是非この小学校の生徒達や保護者、近隣の住民のために公開演奏をしてもらえないかとのことでした。
私たちも吹奏楽コンクールの本番を半月後に控えておりましたので、このタイミングで「聴衆」の前で演奏を披露できることはとてもプラスとなりそうです。協議するまでも無く二つ返事で承諾しました。
ただ一つ心配されたのは司会進行、解説を務めることになったY・O先生のトークでした。
何しろ「難癖オーケストラトップ」の立場で件のキュイに負けずとも劣らない毒舌に磨きをかけられ、「スピード違反の罰金は必要経費」と何の躊躇いもなく堂々と発言なさる方ですので、純真な小学生たちを前に彼らの将来に影を落とすようなお話、深刻な「ダメージ」を与えるような言葉、今後の成長面で「トラウマ」になるような内容だけは絶対に・・・と、祈るばかりでした。
果たして、無事に問題無く「本番」を乗り切れるのでしょうか・・・。
---第13話に続きます(※次回からは不定期更新となります)---
(文/浅香満/日本・ロシア音楽家協会、日本作曲家協議会、日本音楽舞踊会議 各会員)
一覧に戻る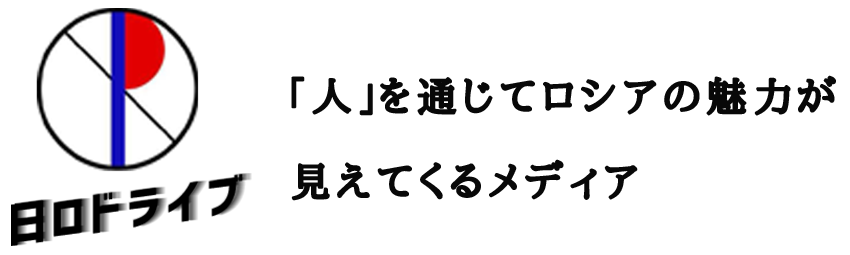

 2021.01.27
2021.01.27 
