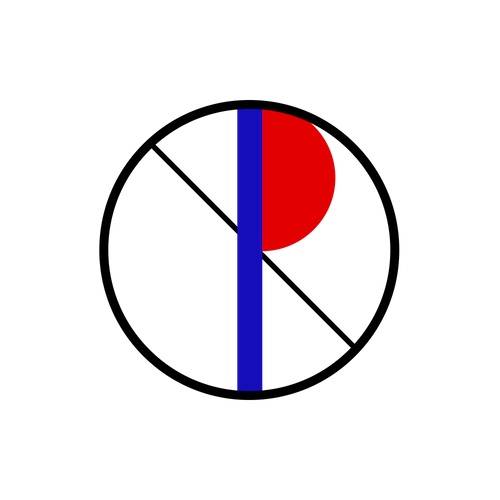ロシアを始めとした世界各地で開催される国際音楽祭に度々招かれるなど、世界を舞台に活躍されていらっしゃる音楽家・作曲家の浅香満さんのコラム「ロシア音楽裏話」第11話です。
前回までの連載記事はこちらから
(以下、浅香さんのコラムです)
.
.
.
.
.
1993年にロシア、タタールスタンの首都カザンで開催された「ヨーロッパ・アジア国際音楽祭」で拙作を演奏してくださる国立管弦楽団首席クラリネット奏者のA・グリファノフ氏のパフォーマンスにリハーサルで初めて接し、日本で学生時代に学んでいた楽器表現の最も重要な謂わば「本質」が根底から覆されるのを目の当たりにすることになりました。
作曲家を志す者はその修業時代に作曲実技、理論と並行して音楽そのものの表現媒体である楽器について研究しなければならず、その個々の楽器については勿論のこと、複数の様々な楽器が組み合わされることによってどのような効果が生まれるのか等を「管弦楽法」を通じて学んでいきます。
ですが、この分野で大変お世話になった師匠がT・M先生で、世界的な作曲家であるだけでなくTV番組の司会、CM(先月お話した化粧品だけでなく、M社の車のイメージキャラクターも務められ、実は高級外車を乗り回されているという噂の中、律義にも大学にはそのCMに登場する全く同じボディーカラーのM社の乗用車で通勤されていました)更には右翼の活動家としても注目を浴び、要するに多忙を極めておられていたため、大学でのせっかくの貴重な授業、レッスンが「休講」となってしまうことが多く、当時は「休講」の場合、構内の掲示板に「〇〇教官、〇月〇日、〇時限目、科目名:〇〇、レッスン名:〇〇 休講」という大学事務職員直筆(なかなか達筆でした)による「手書き」の紙がその都度貼られるのですが、T・M先生はあまりにも休講が多いため、いつしか日付以外の箇所が「コピー」となっておりました。(先月お話いたしましたように時には授業、レッスンが一年間に僅か2回しかなかったこともありました
他の「管弦楽法」を担当されている先生の授業、レッスンは定跡通り個々の楽器の解説から始まってアンサンブルの効果等、順序だてて講義形式で行われているようなのですが、我らのT・M先生はお忙しいためか、滅多に大学にいらっしゃらないためか、そのような講義は一切なく、ただひたすら「実践あるのみ」です。
先生は常日頃から「芸術家を志す者は『教わろう』と思ってはいけない。芸術の本質に迫ろうとするマニュアルなど存在しない。自分が良いと思った楽曲や感銘を受けた作品から先ず『盗み取り』自らの精神の中で昇華させろ」との持論を展開されていました。
多方面で活躍されている先生ならではの「正論」で、なるほど「待ち」の姿勢ではなく積極的に「攻めて」こそ真の芸術家としての道が開けるのだなと当時深い感銘を受けたものです。
因みに私も現在「教える」立場にもなっている訳ですが、弟子としてはこの師匠の言葉、教訓を是非受け継ぐべきであると考え、自分の教育の現場でも生徒達に語って聞かせおります。
そこで気付いたことなのですが、この手法ですと事前の授業準備が著しく簡略化できる・・・もっとはっきり言えば殆ど何もしなくてよいことがわかり、さすがT・M先生!と妙に納得するのでした。
さてそれはともかく話を戻しますと「実践あるのみ」に従って最初からいきなり「ピアノ曲を管弦楽用に編曲せよ」というような課題が出されることになります。
例えば忘れもしない初回はドビュッシーのピアノの名曲「月の光」をオーケストラに直せというものでした。
そして弟子たちが手掛けたスコア(オーケストラの全ての楽器が何を演奏しているのかが書かれている総譜)を手にした師匠を弟子達がぐるりと囲むように着席し、楽譜を読み進める師匠の目とどのような言葉が発せられるのかという期待を込めて口元に全員が集中するのでした。
この時のトップバッターは私と同期のT・H君で、師匠が楽譜を2ページほど捲ったところで「フッ」と深い溜息をつかれました。
一体どうしたものかと弟子たちに緊張感が走ります。
そして徐に楽譜の中の打楽器パートを指し示して「何!?ここで銅鑼!?」と少し大きな声を上げました。
その瞬間、教室内は大爆笑に包まれます。
彼は前半部分の抒情的な美しい旋律が流れ始める箇所に何と銅鑼を叩くようにと指定していたのでした。
銅鑼という打楽器は、例えば船が出港する際の見送りの時などに派手に叩かれる金属製の大きなゴングのようなもので、静謐を湛えた「月の光」には何とも不似合いな楽器と言えるでしょう。
師匠を取り囲む、特に経験豊富な上級生たちがその非常識な楽器の扱いに思わず反応してしまったところですが、実は師匠が指摘した箇所に対する門下生たちの反応、特に不適格さに対する嘲笑の大きさこそが「いかに可笑しいのか」を示すバロメーターになっていたのでした。
私も周りに釣られて・・・と言うよりも周り以上に大きな声を上げて笑ってしまったのですが、正直に言えば自分が手掛けた編曲の中の似たような箇所にも同じく銅鑼を使っておりましたので、人目につかないところでそこに書いてあった銅鑼のパートを慌てて削除したのでした。
T・M先生の担当は「管弦楽法」つまり「楽器の使い方」の師匠ではありましたが、何しろ世界的に活躍され注目を浴びている神様のような存在でしたので、単に楽器使用法に留まらず、「作曲実技」そのもののレッスンをしていただくこともありました。
実技レッスンの形態は「管弦楽法」と同様に学生が書いてきた楽譜を前にした先生を弟子たちがぐるりと囲み、全員でその楽譜を覗き込みながら先生の言動に細心の注意を払うといった形です。
しかしながらT・M先生は多忙を極める活躍の日々でしたので、1度レッスンを受けると「次」はいつになるかがなかなか決まらず、かなり間隔が空いてしまうことも珍しくありませんでした。
下記はT・M先生の「一番弟子」で大学院に在籍され、先生のTV番組でもしばしば編曲の手伝いをされているY・T先輩のレッスンでの一コマです。先生はY・T氏の楽譜のある箇所を指し示し感激しながら、
「君、ここは格段に良くなったね。前と見違えるように進歩したよ。君がいかに努力したのかが如実に表れている。さすが、Y・T君だ!」と絶賛されたことがありました。するとY・T氏は喜ぶかと思いきや、少し困ったような表情になり
「あのう・・・そこは前と全く同じです。何も変更していません・・・」
(T・M先生)「・・・・・」
レッスン間隔が空いてしまうと、いかに世界的に活躍されている先生でも記憶力が怪しくなるようです。
因みにT・M先生は「毒舌家」として知られ、様々な分野での発言も如何なる忖度もなく率直になさり、その歯に衣着せぬ物言いが人気に繋がっている方でしたので、我々の授業やレッスンでもてっきり辛辣な言葉が毎回浴びせられるものと覚悟していたのですが、そこはさずが、「人を育てる」術にも長けていたT・M先生です。
弟子がレッスンで必要以上に落ち込まないようにときめの細かい配慮をされていたのでした。
因みに他の作曲科の先生方は、外部に対して殆ど「尖った」発言をなさらないのにもかかわらず、中には積りに積もったストレスをレッスンで発散させようとしているかのように、ちょっとした記譜上のミスについてもまるでその学生の全人格を否定しているかのように責め立て、その影響で暫く家から一歩も出ることができなくなるくらい絶望させられた学生を多数輩出した「大先生」も少なからずおられました。
学生に対して思いやりを持ってアドバイスを与えるT・M先生はどちらかと言えば貴重な存在でしたが、滅多に大学に出講されないことで時にはそのちょっとした「気遣い」が地雷を踏んでしまうこともあった訳です。
「一番弟子」のY・T先輩は学生時代からその才能を注目され、卒業後も師匠であるT・M先生の期待を決して裏切らない活躍をされていました。
作品は国内外で演奏され高い評価を得ていました。
その作曲活動の中でやはりロシア、タタールスタンで頭角を現し、国際的な評価を獲得しつつあったラシッド・カリムリン氏と知り合うこととなり、二人は強い友情の絆で結ばれることとなりました。
そしてカリムリン氏の本拠地であるカザンで先ずY・T先輩の作品が紹介され、その演奏家の表現力の豊かさと運営スタッフの心遣いにいたく感激した先輩は、この機会を設けてくれたカリムリン氏を何と「自費」で日本に招待しました。
実は「ロシア国籍」の人間はビザの取得が容易ではなく気軽に海外に出ることができない中、Y・T先輩の尽力によってカリムリン作品も日本で紹介され、この出来事がきっかけとなってすっかり日本が気に入ったカリムリン氏は自らがトップを務めるタタール作曲家同盟に働きかけ、スポンサー探しにも奔走してくださって「ヨーロッパ・アジア国際音楽祭」を立ち上げ、参加国中、日本から最も多い人数をこの音楽祭に招待してくださったのはこのような経緯によるものでした。
つまり、ロシアで私の作品も演奏していただけるという栄誉は、この偉大なY・T先輩の功績無くして実現されることは無かったといえます。
学生時代の当時はY・T先輩は後輩達誰もが皆憧れる謂わば「雲の上の人」でしたが、この時の「ご縁」が発展し大きなチャンスをいただけたことに思い返すたびに感謝の念が強くなります。
因みにY・T先輩が「雲の上の人」であれば、指導してくださったT・M先生は差し詰め「宇宙の彼方の存在(!?)」と言えるかもしれません。今考えると本当に恵まれた環境の中での貴重な「ご縁」をいただけたという実感が深まっていきます。
話をT・M先生の「管弦楽法」のレッスンに戻しますと、既に「生の」オーケストラによって数々の作品が演奏されていたY・T先輩への先生からのアドバイスは時にはコミカルなやり取りはあったものの、相対的にはより実用性重視のレベルの高い内容でしたが、いかんせん私や同期のT・H君のようにまだ一度も書いた譜面がオーケストラの「生の」音で披露されたことがない弟子達、謂わば「管弦楽法」の超初心者の楽譜は先生の頭を大いに悩ませたようです。
そこには楽器の特性を活かし切れていないものはまだしも、明らかに演奏不可能なものもあれば、そもそもその楽器では出せない音や音型も散見され、その惨状は先生曰く「地獄絵図」を眺めているようだと評され、それでも他の先生方のように基本を「教える」という姿勢に転じるということは全くありませんでした。
そこで、次に先生が取った行動は「オーケストラのために書いた譜面が音になった経験がないなら、実際に音にしてみたらいいじゃないか」ということでした。
つまり学生が編曲したものをオーケストラに「実演」させてみるということです。
果たしてそのようなことができるのでしょうか?弟子たちが疑心暗鬼になっていたところ、そこはさすが世界のT・M先生です。
私達が学んでいた音大には「管弦楽研究部」というセクションがありました。
これは一言でいえば教員によるオーケストラで、指揮科の学生の実技、器楽科の学生の協奏曲の伴奏、オペラの伴奏等も担当するのですが、教員自らがオーケストラの奏者となってより理想的なアンサンブルの方向性や指導形態を文字通り「研究」するためのセクションではあるのですが、「研究」のためにはノーマルな視点では目的が達成できないため、敢えてどうでもいいことにも難癖をつける習慣が蔓延し、奏者は次第に偏屈者と化し、その結果ここの楽団員は業界でも一癖も二癖もある曲者、強者揃いとなり、共演した学生は皆何度も泣かされ、日本一扱いにくいという悪名轟くオーケストラへと変貌を遂げたのでした。
したがってこのオーケストラの練習所にすら授業、レッスンの目的以外で近寄る者も無く、宛らマフィアの巣窟のように思われていました。
しかし、何の忖度もしないT・M先生はこの偏屈難癖オーケストラに「管弦楽法」超初心者の未熟な学生達の書いた楽譜を実演させ、曲者奏者たちから直接率直な意見を伺う、これは即ち罵詈雑言を容赦なく学生達に浴びせようという残酷極まりない死刑宣告にも等しい罰ゲームのようなことを考えついたのでした。
---来月更新予定の第11話に続きます---
(文/浅香満/日本・ロシア音楽家協会、日本作曲家協議会、日本音楽舞踊会議 各会員)
一覧に戻る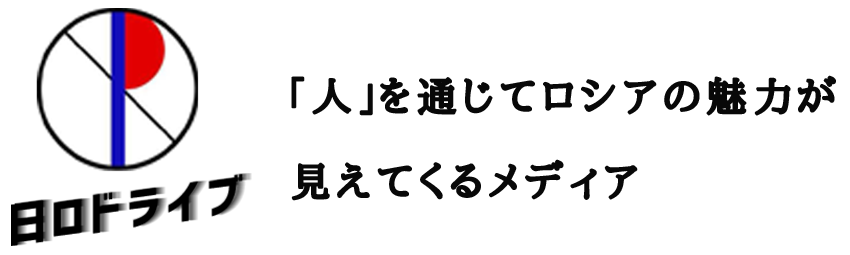

 2020.11.26
2020.11.26