ロシアを始めとした世界各地で開催される国際音楽祭に度々招かれるなど、世界を舞台に活躍されていらっしゃる音楽家・作曲家の浅香満さんのコラム「ロシア音楽裏話」第4話です。
前回までの連載記事はこちらから
(以下、浅香さんのコラムです)
.
.
.
.
.

8月は終戦記念日がありましたので、関連の記事を多く目にしました。
中でもロシアで終戦を迎え、捕虜となった旧日本軍兵士のエピソードに目が留まりました。
「日本に帰ることができる」と知らされ、喜び勇んで列車に乗ったところ、到着したのは祖国に向かう船が出る港ではなく「シベリア」であり、強制労働が待ち受けていた・・・という記事には心が痛みました。
例として適切性を欠くかもしれませんが、「迅速」に目的を果たすためには手段を択ばず、謂わば「何でもアリ」的な発想は脈々と受け継がれているようで、音楽祭送迎担当スタッフが出発予定時刻を過ぎても依然として夢の中にいる国際音楽祭出演者を「迅速」に送迎バスに乗車させるために「火災発生」とまで偽ってベッドから引き摺り出し、あっという間に任務を完了させた手腕には驚かされたものです。
そのため、パジャマ姿の者、下着にコートをひっかけただけの者等、「リハーサル」だけのスケジュールとは言え、殆どのメンバーが外出向きとは言えない部屋着姿でバスに乗り込み、その大半は「リハーサル」に向かうというよりも単に「避難」する感覚だったことでしょう。
そして到着した立派すぎる「リハーサル」会場には赤い絨毯が敷かれ、美しい民族衣装を纏った若い女性たちが花束を持って待ち受けてくれ、テレビカメラが回り、フラッシュが焚かれ、狼狽えるパジャマ氏や下着氏を筆頭に動揺を隠せないメンバーは「完璧に正装」したスタッフに案内され、「最高会議室」に通されました。
ほぼ全員が「緊急避難」用に部屋着にコートを引っ掛けてきただけという恰好でしたが、入口のクロークでコートを預けない訳には行かず、特に下着氏やパジャマ氏は最後まで抵抗していたようですが、「完璧に正装」したスタッフに諭されて渋々コートを脱ぐことになってしまいました。
事前のインフォメーションによると本日のスケジュールは「リハーサル」だけとなっていたのにもかかわらず「市長主催の歓迎会」が行われている現実を目の当たりにして「話が違う!!」という洗礼を再び受けることになりました。
「歓迎会」は市長の挨拶とウォッカの乾杯でスタートしました。
皆さんもご存知のことと思いますが、この「ウォッカ」はロシア語の「水」の指小形、つまり「愛しの水」というニュアンスを持っていて、ロシア人にとっては切っても切り離せない飲み物となっています。
アルコール度数は40度以上あり(中には96%!!というものまであります)これをちびりちびりとはやらずに俗に「喉で飲む」と言われているように「一気飲み」するのです。
念のために付け加えておきますと「一杯」のグラスは小さなものです。
最近ではウォッカの人気が下降気味という話も耳にしますが、この「スピーチと乾杯」をセットにして何度も繰り返されるのが、昔からの「ロシアの伝統」となっており、この地はタタール人の国、「タタール自治共和国」ではありますが、ロシア連邦の一員としてこの伝統は確実に受け継がれているようです。
前にも書きましたが、タタールスタンは飲酒を禁じる「イスラム教」を「国教」としているのですが、歓迎会ではウォッカなのです。
更に言えば、その土地ならではの「地ウォッカ」なるものまで存在し、ここ首都カザンで生産されたウォッカは全ロシアでのコンテストで優勝したこともあるそうです。
何故、飲酒を禁じる宗教を国教としているこの地で地ウォッカのチャンピオンが誕生しているのか?・・・深くは考えないことにしましょう。
何しろ「日本の常識」の尺度では測りきれないところなのですから。
市長に続いて地元の有力者、スポンサーから次々と歓迎の言葉をいただき、その都度「乾杯」となります。
ちなみにロシア語で「乾杯」は「ザ・ズダローヴィエ」と言い、これは「健康のために」という意味になりますが、この40度を超えるアルコール度数を誇る「愛しの水」を一気飲みすることは想像するまでもなく大きなリスクを伴い、18歳にしてアル中であったムソルグスキーを筆頭に多くの作曲家、音楽家、芸術家、文化人のみならず政治家、一般人に至るまで「健康のため」の乾杯が愛飲家の寿命を縮める結果になっていたことは言うまでもありません。
ちなみに、訪れた1993年当時のロシア人男性の平均寿命は60歳にも達しておらず、その二大原因の一つが「愛しの水」にあったことは明白です。(※もう一つの大きな原因は「交通事故」だそうです。なお、現在のロシア人男性の平均寿命は67歳まで延びました・・・それでも67歳!?)
脱線のついでに追加でお話しますと、モデスト・ムソルグスキー(1839-1881)は、このコラムの初回に登場したボロディンと共に所謂「ロシア五人組」(バラキレフ、キュイ、ムソルグスキー、リムスキー=コルサコフ、ボロディン)として音楽史上に燦然と輝くメンバーの一人として大活躍した・・・と言いたいところなのですが、メンバーの中では最も才能が劣るとされ、このグループのリーダーで師匠格のバラキレフから「ハエ」呼ばわりされるくらいでした。
そのような彼が今日では、その独創性を誰よりも高く評価され、メンバーの作品の演奏回数でもダントツであることも何とも皮肉な結果と言えましょう。
ただし、日本の義務教育の音楽の授業でも愛聴されている交響詩「禿山の一夜」や組曲「展覧会の絵」、ロシアオペラの最高傑作として名高い「ボリス・ゴドゥノフ」はムソルグスキーの「代表作」として高く評価されているのにもかかわらず、当の作曲者本人は今日演奏されている形では何と「一度も聴いたことが無い」という摩訶不思議な現象が起きています。
自分の代表作を全く聴いたことが無いというこの不思議な作曲家は、4度の心臓発作を起こした末に亡くなったと伝えられていますが、18歳からアル中であったが故に心臓が肥大し、それのみならず肝臓破壊、腎臓腐敗、脊髄の炎症、てんかん性発作というように ありとあらゆる内臓疾患、神経異常に侵され、まるで病気のデパートとでも言うべき状態に陥ってしまいました。
「仲間」のボロディンは医学博士でもあった(※本当はこちらが本業)ことから、彼の配慮により一般の人ではなかなか入院できない最上級の病院(※陸軍の病院、ムソルグスキーは一時陸軍の軍人でもありました)で手厚い看病を受けていたのにもかかわらず、彼自身の手によって悲劇の幕が切って落とされます。
彼の誕生日は3月21日、そして命日はジャスト1週間後の3月28日です。
しばしば意識が朦朧となっていた彼は、本来の誕生日から1週間経過してしまった3月28日を誕生日であると「勘違い」してしまい、何としても「祝わなければ」という思いに駆られてしまいます。
ムソルグスキーの元には、仲間や彼を慕う支援者たちから「治療費に充ててほしい」との心遣いから多額の寄付金が集まってくるのですが、彼はこともあろうに使用人にその「治療費」でコニャック2本を買いに行くように命じます。
そして、その2本を立て続けに浴びるように飲み干してしまい、結局それが「致命傷」となって亡くなりました。
彼の最後の選択がウォッカではなくコニャックであったのは、コニャックの方が高級で価格も高く、「誕生日」という特別の日を祝うためにグレードアップしたためと思われます。
多くの謎と矛盾が混在する、ある意味ムソルグスキーらしい42歳になった直後の最後であったと言えるでしょう。
ちなみに葬儀委員長は決して彼を「ハエ」呼ばわりすることのなかった真の「仲間」であるボロディンが務めました。
鬼のように(※ロシア人の例えとして不適切かもしれませんが)怖く厳しく周りからも恐れられていたリーダー、バラキレフから「ハエ」とあだ名されても「ハエならハエで結構、音を立てて飛び回ってやる」と立ち向かっていったムソルグスキーの気骨の背景には、その原動力としてのアルコールは必要不可欠であったことでしょう。
なお、バラキレフの出身大学はこの地の首都にあるカザン大学(※専攻は数学)です。
「愛しの水」ウォッカはいかなるネガティブな感情をも払拭し、いかなる危機的な状況に於いても前向きな行動を促し、いかなる不利な環境でも魂を奮い立たせる「魔法」を有し、ロシアの歴史を形作る上でも先の「目的を達成するためには手段を択ばない」手法と絶妙のタッグを組むことで、他国から見れば一見意味不明、不可解、理解不能なことでさえ「正当化」されて輝かしい1ページを飾ることさえ珍しくありません。
このウォッカの恩恵を受けて、それまで歓迎会の席上でメンバーの背後に隠れるようにしていた下着氏とパジャマ氏の「迷」コンビが勢いづいてきました。
4回目くらいの乾杯からその「雄姿」を惜しげもなく堂々と披露し始め、5回目の乾杯の後には何と「俺にもスピーチさせろ」と言わんばかりに下着氏は「下着姿」であるにもかかわらずウォッカのグラスを片手に市長の前に進み出ていき、慌てた同国のメンバーに取り押さえられるという一幕もありました。
この国際音楽祭の総合プロデューサーであるラシッド・カリムリン作曲家同盟チェアマンによる主催者側、出演者側双方への感謝のスピーチで、永久に続くのではないかと思われた歓迎会の幕が漸く閉じられました。
なお、会場内にいた数名は会場奥に用意されていた別室で倒れ込んでいたようです。
歓迎会場では至る所で頻繁にカメラのフラッシュが焚かれ、複数のテレビカメラによる収録も行われていたのですが、通訳のセルゲイさんによると、共産主義時代は「鎖国」政策で国外からの出入り禁止となっていたため、これほど多くのしかも音楽のトップレベルの実力を有する芸術家(※この表現に今回の取材陣は疑問を抱いたかもしれませんが)が一堂に会するのが共産主義崩壊後「初」であったため注目度が極めて高く、地元タタールスタンは勿論のこと、モスクワをはじめとするロシア国内のみならず、ヨーロッパの他の国からも報道陣が多数集結していたそうで、つまり美しく着飾ったご婦人方、完璧に正装した「歓迎する側」と、外出も憚られるような部屋着姿が大半の「歓迎される側」とが成す絶妙なコントラスト、そして下着氏やパジャマ氏の「雄姿」も世界中に配信されたのでした。
実際、この歓迎会の様子は早速地元有力紙の当日の夕刊第一面を飾り、その第一面での集合写真では下着氏とパジャマ氏は臆することなく最前列に陣取り、一際目立っていました。
なお、第一面の見出しでは次のような活字が躍っていました。
「全く気取らない世界の音楽家たち」
---来月更新予定の第5話に続きます---
(文/浅香満/日本・ロシア音楽家協会、日本作曲家協議会、日本音楽舞踊会議 各会員)
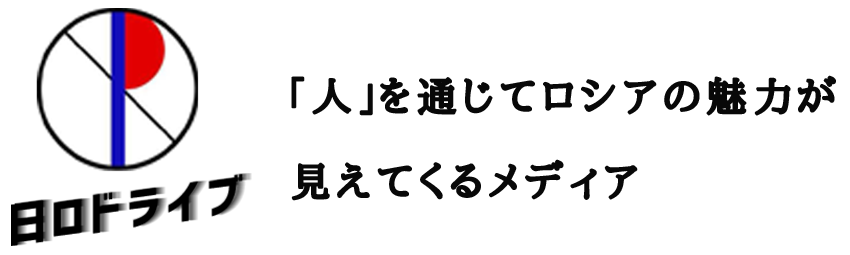

 2021.01.27
2021.01.27 
