これまでに、日本とロシアに関わりのある「人」にフォーカスし、インタビュー記事を掲載してきた「日ロドライブ」ですが、知り合ってきた方々とのご縁もあり、今月から、日本とロシアに関わり、交流を続けている方々のコラムなども掲載させていただけることになりました。
記事を書いてくださる方は、どの方も魅力的な方々ばかりで、コラムの内容も、興味深く、それぞれに特色があって、とても面白いものになっています。
今回は、これまでにロシアを始めとした世界各地で開催される国際音楽祭に度々招かれるなど、世界を舞台に活躍していらっしゃる音楽家・作曲家の浅香満さんのコラム「ロシア音楽裏話」第1話です。
(以下、浅香さんのコラムです)
.
.
.
.
.
私が初めてロシアに渡航したのはソビエト連邦崩壊からまだ2年も経過していない1993年の11月でした。
モスクワから約700キロ東に位置するカザンで開催された「ヨーロッパ・アジア国際音楽祭」の主催者からの招待を受け、所属する日本作曲家協議会のメンバーを中心に作曲家5名、演奏家2名(演奏家は2名とも作曲家の奥様)の計7名で向かいました。
事務局より「11月のロシアはとても寒いから」「とにかく半端なく寒いから」くれぐれも気を付けるように、特に飛行機を降りた直後が要注意であり「温度差」にやられる、モスクワの空港は暖房なんて効いていないと思え、初っ端で体調を崩したらこの後の音楽祭は「地獄」のようになる、等々散々脅かされていたので、モスクワに着陸後の降機直前にマフラーに手袋、厚手のコートに身を包み、以前にもロシア滞在の経験のあるメンバーに至ってはミンクの帽子まで被った「完全防備体制」で降り立ったところ、気温は何と20度!!もあって全員で「話が違う!!」と叫んだものです。
勿論、忽ち汗だくです。
さらにこの後、夜行寝台車でモスクワからカザンまで13時間の移動となるのですが、この車内は信じ難いことに30度!!!の「蒸し風呂」状態で、執拗な要請による防寒対策でラクダの下着を着用していたメンバーはまるで茹でダコのようになっており、(よりによってそのメンバーは体格が良く---と言うか横幅が私の1.5倍もある巨漢)事務局の心配とは逆の意味で体調を崩しそうになりました。
因みにこの寝台車は窓の開閉禁止です。
早くも事務局の想定とは別の「地獄」を味わった訳ですが、思えばこれは「話が違う」のほんの序の口に過ぎず、この後数多くの驚きの「話が違う」が待ち受けていることなど、この時は想像もできませんでした。(後で聞いた話ですが、モスクワのこの時期の20度はやはり「異常気象」で、一週間後には雪景色に様変わりしました)
当時のカザンには日本人は僅か二人しか住んでいませんでした。
一人はNHKの駐在員、もう一人はこの地の出身者が日本に滞在していた頃に知り合って結婚され、その後一緒に帰郷された「日本人妻」です。
したがって、日本ではあまり知られていなかった都市でしたが、2018年のサッカー、ワールドカップで日本代表チームのキャンプ地となったことで一躍有名になりました。
「ロシア連邦」内でありますが、ロシア共和国ではなく「タタール自治共和国」の首都です。
皆さんご存知のことと思いますが、ロシアに於ける「ロシア人」の割合は約80%に過ぎず、レーニンもスターリンもロシア人ではありません。(二人とも「ペンネーム」で本名ではありません)
ロシア人に次ぐ第二の民族が、アジア系遊牧民族にルーツを持つ(諸説あり、ユーラシア大陸の様々な民族から構成されている可能性もあります)「タタール人」です。
カザンはこの「タタール人」の国の首都ではありますが、ロシア人とタタール人の割合はほぼ半々とのことでした。
因みに作曲家ではボロディン、ラフマニノフが「タタール系」でラフマニノフの名前をキリル文字にしたスペルの冒頭にある「PAXMAH」(ラハマン)はタタール語の「祈り」という意味だそうで、またボロディンにはタタールの王族の血が流れています。
「タタール」を中国語読みすると「韃靼」(だったん)となり、ボロディンの代表作が何故「だったん人の踊り」なのかを解き明かすカギが、自らに流れている血と深く関わっていることは明白です。
この「だったん人の踊り」が登場するのが壮大な歌劇「イーゴリ公」で、これは1185年のロシアとだったんの戦いの「実話」に基づき、作曲者ボロディンが自ら台本の筆も執りました。
当初は台本の専門家が執筆する予定でしたが、それを断ってでも描きたいテーマを「自分の言葉」を重ね合わせて展開することに拘ったところに「タタール王族の血」を受け継いでいるボロディンの執念が垣間見えます。
この物語は「ロシアの英雄的」戦記物と捉えられがちですが、オペラで描かれている主人公「イーゴリ公」はざっくり言えば、民衆の反対を押し切ってだったんに戦いを挑んだものの、その結果は「全滅」、そして息子とともに捕虜となってしまい、最終的には隙を見て逃げて帰ってくる「だけ」です。
「ロシア軍全滅」の悲報を受け、イーゴリ公の身を案ずる妻の許に生還したことで何となくハッピーエンド的な雰囲気となり「幕」を閉じるのですが、台詞の中には勇ましい言葉も散在しているものの客観的に見てさほど「英雄的」な要素はありません。
オペラとしてはここで「幕」なのですが、先述したようにこの物語は「実話」に基づいていますので、さらにその先、史実ではどうなっているのかと言えば、イーゴリ公はロシア軍を立て直し再びだったん軍に戦いを挑みます。(この「決意」はオペラの中にも表現されています)
果たしてその結果は----何と、またしても全滅!!--です。
対して、だったん軍の総大将コンチャック汗は、本来であれば戦で勝利した際、見せしめのために敵方の首を切ったり串刺しにするのが慣例になっているのにもかかわらず(オペラの中にも「首切り」「串刺し」という言葉がコンチャック汗の口から発せられる場面があります。
また、諸説ありますが、一説によるとこのような残忍な行為に平気で及べる民族は「地獄の使者」に違いないということからギリシャ神話の地獄の使者を意味する「タルタロス」が「タタール〜だったん」の語源となっていると考えられていますが、当のタタール人はこの説に否定的です) 殺害するどころか鎖につないで幽閉することさえせず、まるで「客人」のようにもてなすのです。
件の「だったん人の踊り」(正式にはポロヴェッツ族であることから海外では「ポロヴェッツの踊り」と呼ばれています)はこの「おもてなし」として全滅で意気消沈したイーゴリ公を慰める宴の場で繰り広げられる踊りです。
更にコンチャック汗は戦いではなく講和を持ち掛けたり、同時に捕虜となったイーゴリ公の息子と自分の娘との間に芽生えた愛情を妨害するどころか祝福し、また闇に紛れて逃走するイーゴリ公を目撃しておきながらも追っ手を差し向けることもせず・・・と言うように「主人公」であるイーゴリ公よりも遥かに「器の大きな人物」として描かれています。
このようにだったん(タタール)の王族の血を持つボロディンならではの「だったん側」の視点が込められているのですが、多くの演出家がその意図を理解せず一方的な「ロシア側からの視点」のみで、だったん=敵、コンチャック汗=悪者として必要以上に描きたがるのが残念なところです。
また、ボロディンは生前にこの大作を完成させることができなかったため仲間の手によって何とかステージにかけられる形にはなりましたが、如何せん終盤の充実度が不十分で、もしかしたら終幕前に台本に自らの主張を加えたかった可能性も考えられます。
少し長くなってしまいましたが、このようなタタール人(だったん人)の都であるカザンで開催されたのが「ヨーロッパ・アジア国際音楽祭」です。
もうお分かりのことと思いますが、何故この地でこの名称の音楽祭が企画されたのか、その理由はここが「洋の東西が交わるところ」だからです。
---来月(6月)更新予定の第2話へ続きます---
(文/浅香満/日本・ロシア音楽家協会、日本作曲家協議会、日本音楽舞踊会議 各会員)
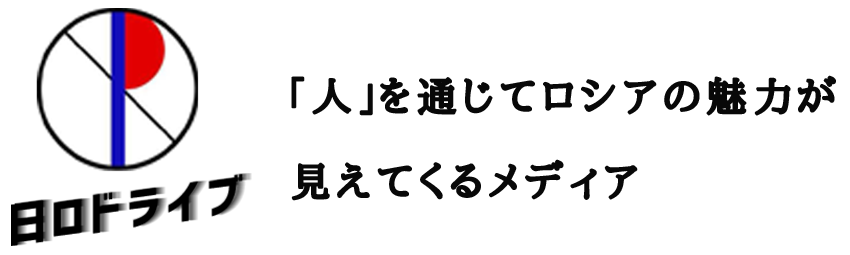

 2020.12.30
2020.12.30 
