ロシア外務省を発起人とする雑誌、「考える人のための外交雑誌『国際生活』日本語版」の編集長である安本浩祥さんによる連載コラム「外交雑誌編集長の『ちょっとうがった世界の見方』」が日ロドライブでスタートします。
ロシア及びヨーロッパ・アジア各国との民間外交に貢献することを目的とする「(一社)欧亜創生会議」の理事長でもあり、過去には、ロシア国営放送「ロシアの声」のアナウンサーをしていた経歴も持つ安本さん。
本コラムでは、そんな安本さんならではの独自の鋭い視点が光ります。
-----
こんにちは、「考える人のための外交雑誌『国際生活』」の日本語版編集長を務める安本です。
このコラムでは、「国際生活」の記事をきっかけにして、皆さんに普段とは違う視点を提供することができれば幸いです。
今回は、2021年7月30日の記事「ブルガリア、ワクチン接種の判断ミスにより1万人が死亡」について考えてみたいと思います。
タイトルだけ見ると、ワクチンを接種する時の何らかの医療ミスによって1万人が死亡した事件のように思われるかもしれません。
しかし実際には、もしも高齢者などのハイリスク群に優先接種をしていれば1万人近くの人々が死なずに済んでいただろう、という内容で、高齢者への優先接種をしなかったという政府の政策判断を非難する内容になっています。
つまり、政府が政策判断を誤ったため1万人が亡くなった、もっといえば、国が1万人を殺した、ということをこの記事では言っているのです。
今回のコラムは、どうもこのような考え方には違和感を感じざるを得ない、というところを出発点にして考えていきたいと思います。
もちろん、何の違和感も感じない、という方は今回のコラムはパスしていただいて、また次回、機会があればお会いしましょう。
「国が1万人を殺した」という考え方の根拠とは?
「国が1万人を殺した」という考え方の根拠という考え方の根拠は、主に2つ考えられます。
第一に、国が十分な量のワクチンを確保していれば多くの人が助かったはずであり、その確保の努力を怠った政府は、1万人の死亡に対して責任を負うべきだ、というものです。
しかし、そもそも世界的にワクチンの絶対量が不足しているなかで、自国の人間がより多く助かったところで、他国の人間がより少なく助かることになるため、国を超えた問題であり、一万人の死亡を一国だけの責任に帰すことはできません。
強いて誰かの責任に帰すのであれば、それはワクチンを製造する医薬品メーカーということになるでしょうか。
しかし、ワクチンの数が不足しているとはいえ、少なくとも助かった人間もいるわけですから、医薬品メーカーはその助かった人間に対しては有益なことをしているのです。
そして、いまだ助けられていない、つまりワクチンがいきわたっていない人に対しても、なにか有害なことをしているわけではありません。その人の死を早めるようなことはしていないからです。
自然に発生するウイルスに感染して死ぬ、ということは、そもそも自然なことであり、誰かの責任を問うべき性格の事柄ではありません。自分の生に責任を負うべきは自分のみであるべきです。
さもなければ、自由というものを失うことになるでしょう。
第二に、限られた数のワクチンであるとはいえ、ハイリスク群に優先的に接種をしていれば、今回の1万人のうちの多くは高齢者であったから、助かっていた可能性が高い、よって1万人は政府の「優先接種をしない」という政策判断のミスによって死亡したのであり、国はその責任を負うべきである、という考え方があります。
しかし、ハイリスク群はそもそも死亡率が高いのが当然であり、医療費や介護の負担を考えた時、政府としてはある意味で「合理的な判断」をしたという見方もできます。
そもそもハイリスク群に限られたリソースを重点的に投下するべき根拠はどこにあるのでしょうか。
延命のための延命を求めるのは誰なのでしょうか。
それはそこから経済的な利益を得るところの医療産業および介護産業だけである、といううがった見方さえ成り立つでしょう。
人々が求めるものは、本人も周りも納得できる形で死を迎えることであり、何が何でも命を救うことではないはずです。
ハイリスク群の人々とその周りが、そのような心の準備をできていなかったのであれば、それはそのような態度(生を当然視する)に問題があると言わざるを得ません。
現代における医学の宗教化
ここまで考えてきて気付くのが、「死」というものを絶対的な悪として見る考え方です。
もちろん、「悪い死」や「善い死」というのはあるかもしれませんが、なぜ「死」という自然現象をもって悪と決めつけるのでしょうか。
その背景には、医学というものが現代における宗教になっていることがあります。
かつての宗教はある意味で、死を受け入れる準備をさせるものでした。
その宗教に対するライシテ闘争、社会の世俗化が進む中で、医学は「死を遠ざける」という教義によって、現代世界において新しい宗教として君臨しているのです。
実は、今回の記事で問題になっているのは、神聖なものとされてきた医学への信頼が、コロナパンデミックを前にして揺らいでおり、この不安をいかにして「誤魔化すか」ということなのです。
例えば、「医療従事者の皆さんに感謝しよう」というようなキャンペーンが、日本でも行われました。
このキャンペーンの裏で、どれだけの会社が倒産し、どれだけの人が失業したのでしょうか。なぜそのような人たちを差し置いて、医療従事者の皆さんに拍手をしなくてはいけないのでしょうか。
失業した人への連帯を示すことがまずは大切な「人間らしい反応」だったのではないでしょうか。
もちろん、「命がなければ失業もない」という考え方もあるでしょう。
しかし、私たちはいまお互いに生きている人間として社会を形成しているわけですから、命があるからいいよね、という考えでは、社会の問題はなにも解決しないわけです。
医療従事者はどちらかといえば社会的には強者にあたります。
一方、今回のパンデミックで一番のしわ寄せを受けた人々、失業した人々は、社会的には弱者です。
このようなキャンペーンがなぜ行われたのか。なぜ、社会的な弱者への共感を脇においてまで、人々は社会的強者への拍手を求めたのか。
それは「死を絶対悪とする」現代の宗教であるところの医学、人々の信仰の対象である医学が、パンデミックを前になすすべもないのを見た人々が、自らの混乱を収めるため、「自分たちの信仰は間違っていないんだ」と自らに言い聞かせる行為、誤魔化しの行為なのだといえます。
今回のブルガリアのニュースでも、あたかも政府は人命に責任を負うべきであるかのような報道がなされています。
人命に責任を負うならば、政府は必然的に医療と一体化し、医療は国家宗教となります。
実際、いまや先進国と言われる多くの国々で、医療の国家宗教化を見ることができます。
現代の大学医学部で教えられているところの医学は、果たして唯一絶対のカトリックなのでしょうか。
宗教改革、反宗教改革を経て、現在の世俗化された世界で、宗教はかつての力を失いました。
医学もおそらく、将来から振り返れば、今の私たちがかつてのカトリックの中世を振り返るようなことになるのでしょう。
-----
※筆者の主張は個人の見解であり、「国際生活」および「日ロドライブ」の編集部の見方と必ずしも合致するものではありません。
(文/安本浩祥/「考える人のための外交雑誌『国際生活』日本語版」編集長、「(一社)欧亜創生会議」理事長)
一覧に戻る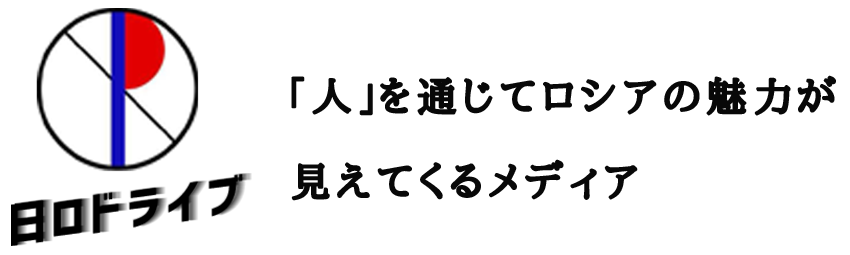

 2021.04.28
2021.04.28 
