ロシアを始めとした世界各地で開催される国際音楽祭に度々招かれるなど、世界を舞台に活躍されていらっしゃる音楽家・作曲家の浅香満さんのコラム「ロシア音楽裏話」第9話です。
前回までの連載記事はこちらから
(以下、浅香さんのコラムです)
.
.
.
.
.
1993年、ロシアのカザンで開催された「ヨーロッパ・アジア国際音楽祭」で演奏される拙作「クラリネット、ヴィオラとピアノのための三重奏曲」は、その前年に国内で初演された作品ですが、もしヴィオラ奏者のY・O氏が電話嫌いでなく「正常に電話が繋がっていれば」この世に存在しなかったかもしれない一曲でしたので、今となってはY・O氏の「電話嫌い」に大いに感謝しなければなりません。
もしこの作品が本当に存在していなかったら、私がロシアの国際音楽祭に招待されることはなかったかもしれませんので。
リハーサルが行われているロシア国立カザン音楽院の練習室から「気合い」の入った音が、練習室の遥か手前から聴こえてきます。
以前、1985年に開催されたショパン国際ピアノコンクール2位受賞者のマルク・ラフォレ氏が完全防音室で練習しているのにもかかわらず廊下まで「音漏れ」していたという記憶が甦り、世界トップクラスは音そのものが「規格外」であることに深い感銘を受け、拙作の演奏者達も皆、この世界トップレベルの音の持ち主であることを確信し、マラート・ザリポフ学部長に感動しながらそのお話をしたところ、「防音室」ではないことを伺って一瞬転倒しそうになりましたが、リハーサルの部屋の扉の前に立ってみると、彼らの音が尋常ではない「伸び」を持って響いていることが実感されました。
これなら、たとえ防音室であってもラフォレ氏と同様に確実に「音漏れ」がしてしまう音質であると言えるでしょう。
一体この音の持ち主はどのような演奏家達なのでしょう。
扉越しに聴こえてくる音の一つ一つに強い情熱が漲り、即座にノックすることが憚られました。
マラート学部長が、お構いなしにノックしようとしたのですが、せっかくの気合の入った練習を中断させたくないという思いに駆られ、失礼かとも思いましたが制止し、少し待ってもらいました。
練習が一段落したキリの良いところで入室し、マラート学部長から演奏者の紹介がありました。
3人とも、この地では珍しく「にこやか」に迎えてくださり、その親しみやすい笑顔にホッと胸を撫で下ろしたものです。
クラリネット奏者のA・グリファノフ氏は国立交響楽団の首席奏者で体格は中肉中背なのですが、複雑な迷路のように絡み合った天然パーマが印象的で丹念に頭髪を調べるときっと何らかの生き物が生息しているのではないかと思わせる風貌でした。
ヴィオラのK・モナシポフ氏は長身のがっしりした体格で腕っぷしも強く最も頼れそうな存在です。
ピアノのY・ソコルスカヤ氏はロシア人(タタール人)としてはやや小柄ながら鋭い眼光を放ち研ぎ澄まされた精神力を発揮され、演奏解釈の司令塔的役割を果たす女性です。
3人ともベテランの演奏家で「国家功労芸術家」の称号を持ち、モナシポフ氏とソコルスカヤ氏は共にカザン音楽院の教授と言う要職にある方々でした。
リハーサルに立ち会って最初に驚かされたのが何といっても先程からもお話している「音質」です。
私のピアノの師匠の師匠がロシア人であったことから、師匠を通じて「ロシア流」の「音作り」の基本を教わってはおりました。
少し専門的な話になりますが、ピアノであれば左右の手から繰り出す響きに慎重に耳を傾け、お互いの音を更に幾重にも響かせ合い共鳴させ合って音質の「厚み」を出していくのですが、おそらく皆様には言葉からだけで想像していただくことが難しいかもしれません。
たとえ左右の手のパートに書かれている音が楽譜上は一つずつしかなくても、その間にある数多くの音を共鳴させ、簡単に言えば楽譜には書かれていない音も引き出して響かせるのですが、彼らはこれを「楽器間」で行っているのでした。
実際に「ロシア流の音作り」を、「ロシア人演奏家自身で作り上げていく現場」を目の当たりにしたことはこれまで一度もありませんでしたので、正に世界のトップクラスの「響きの空間」に居合わせていただけたという実感を味わったのでした。
次に驚かされたのは「異次元」とも言うべきヴィオラです。
日本で初演してくださった先日のY・O氏は日本を代表するN交響楽団の「偉い」立場のヴィオラ奏者なのですが、初演に向けてのリハーサルの際、「こんなの演奏できない」「演奏不可能」を連発されしょっちゅう悲鳴を上げていました。
以前の回でお話ししたサックス奏者に亡命されてしまったS氏の書く作品は難曲揃いで有名でしたが、こと「難曲」に関しては私も負けずとも劣らずで、演奏者によっては「S氏以上」との評価もいただいております。
一説によりますと、学生時代に私の作品の演奏に関わった学生は皆、将来出世するという「伝説」が誕生し、事実、私のピアノの独奏曲やピアノを伴う室内楽作品の殆どを初演してくださったM・Kさんは国際コンクールピアノ部門の最高峰の「双璧」であるチャイコフスキーコンクールとショパンコンクールの両方に日本人として初の上位入賞を果たすという快挙を成し遂げました。
彼女はどのような難しいフレーズを書いてもいとも簡単に弾きこなしてしまうので、ある時、どこまで可能なのかを試したくなり、ピアノパートを五段譜(通常ピアノの楽譜は右手用と左手用の二段譜)にし、それぞれの段を全く異なるリズムで構成し、しかも使用するハーモニーは三和音内、つまりミスタッチをしようものならたちどころに判ってしまうという意地悪三昧の仕掛けを施した曲を書いて渡しました。
しかも、この作品はピアノの独奏曲ではなく歌曲の単なる「伴奏」なのでした。
しかし、その時に限ってどうしても彼女の都合がつかなくなり代わりに彼女の親友Y・Hさんが務めることになってしまったのです。
Y・Hさんはその楽譜を一目見るなりこの世のものとは思えない地獄の叫び声をあげましたが、それでも熱心に取り組んでくださり、本番では何と「完璧」に演奏なさり、母校のピアノ科のレベルの高さに改めて驚嘆したのでした。
なお「代役」で拙作の演奏という洗礼を浴びたY・Hさんもその後、拙作の対極にあるとも言えるモーツアルトを中心とした古典の作曲家作品によるレクチャーコンサートが人気を呼んで全国を回るようになり、近年、K音楽大学の教授に就任され、「出世伝説」を体現されました。
また、ヴァイオリン作品の初演をしてくださったK・S氏はドイツのオーケストラの、同じくヴァイオリンのJ・K氏は日本を代表するオーケストラのそれぞれコンサートマスターに就任され、他にも室内楽作品を初演してくださったメンバーも内外の主要オーケストラの団員として活躍されています。
学園祭で規模の大きな室内楽作品を指揮してくれたK・O氏も今やヨーロッパを代表する一流歌劇場の指揮者、音楽監督となり、作曲者本人を置き去りにして皆さん、出世街道をまっしぐらです。
因みにK・O氏の当時の自慢は「6,500円」の指揮棒でした。これは棒本体は500円なのだそうですが、持ち手の部分に3,000円のワイン2本のコルクを使用したとかで合計「6,500円」なのだそうです。
彼は学生時代から無類の酒好きで、何とこともあろうに私の作品の演奏直前にも飲んでいて酔いつぶれてしまい、楽屋のソファーで横になって死体の如く動かなくなり、本番の時間が迫る中、幾らつついても微動だにせず絶望的な状況に追い込まれていく中、ふとラフマニノフの交響曲第1番の初演時のエピソードが頭の中を過ったことがありました
ラフマニノフは最初、ペテルブルグ音楽院に入学しますが、決して「神童」ではありませんでした。
それどころかろくに音楽院に行かず、当時敷設されたばかりの走行中の路面電車に飛び乗ったり飛び降りたりする「危険な遊び」に興じる「問題児」でしたので、音楽院より退学を勧告されてしまいます。
困った母親は、従兄でもあり、「ピアノの魔術師」ことフランツ・リストの弟子としても知られていた新星ピアニストのアレクサンドル・ジロティに相談し、モスクワにいるジロティの少年時代の師匠である鬼教師、ニコライ・ズヴェレフの元で修行することになり、結果的にここでのスパルタ教育が功を奏しモスクワで才能が開花することになります。
したがって、ペテルブルグとしてはライバルであるモスクワで成功を手にし、その昔「退学」を突き付けた若者がこの地で成功することを望まない風潮があったことから、ラフマニノフの最初の交響曲の指揮を担当する元々大酒飲みであったグラズノフにいつも以上に飲ませ、「酩酊状態」で指揮台に上がらせて滅茶苦茶にし、おそらく「意図的」に失敗させたものと推察されます。
なお「酔っ払い指揮者」に批判の矛先が向かなかったのは、彼がペテルブルグ音楽界の最高権力者であるリムスキー=コルサコフ学院長の弟子であり、何よりペテルブルグ音楽界そのものがラフマニノフの成功を望んでいなかったことが挙げられるでしょう。
これに比べるとスケールは「雲泥の差」ではありますが、誰でも一度は「酔っ払い指揮者」の洗礼を浴びなければならないものなのか・・・と思った瞬間でした。
しかし、そこはさすがK・O氏と言うべきでしょう。
完全に酔いつぶれたと思われたK・O氏でしたが、何と本番1分前に突然カッと目を見開き、何事もなかったかのように軽々とした足取りで指揮台に向かい(グラズノフは千鳥足であったと伝えられています)、「完璧に」指揮をして聴衆の拍手を浴び、終了直後、楽屋に戻ると再びソファーに倒れこんで夢の続きに浸るという離れ業をやってのけたのでした。
この時以来、こいつは只者ではないぞ、きっと「未来の大物」になるに違いないと予感させ、現在その予感を裏切らない活躍をしています。
ところで、卒業して暫く経った頃、ある会合で「何故、拙作の演奏者は出世するのか」ということが話題になり大真面目な論戦が交わされたことがありました。
他の作曲科の学生の作品の演奏に関わった者でも、勿論活躍している演奏家はいるのですが、拙作ほど多くはなく、また「出世」と言っても中には郵便局長になった者、缶詰会社の社長と言った「畑違い」も意外にあり、必ずしも音大出身者が音楽界だけに留まっていないことが浮き彫りとなりました。
厳しいレッスンの何が反映されているのかはわかりませんが、保険のセールスで優秀な成績を残している演奏科出身者もいました。
その論戦の挙句、拙作に携わった演奏家の多くが内外で大活躍している理由が結論付けられました。
それによりますと、多くの演奏家が口を揃えて言うことには、ひとたび私の作品を演奏すると、「これまで難曲とされていた過去の名曲」や「とても手が届かないと思えていた超絶技巧を駆使する作品」が、「まるで子供のための作品みたいに簡単に思えてくる」のだそうです・・・何のこっちゃ・・と思いながらも微力ながら日本の音楽界の発展に陰ながら尽力していた(!?)かもしれないと、密かに自分を慰めております。
話が少し逸れてしまいましたので、元に戻します。
日本での初演時のヴィオラ奏者、しかも「偉い」立場の方が悲鳴を上げながら練習をしてくださったので(「演奏不可能」を連発されましたが、何とか泣きついて楽譜の書き換えや変更はしませんでした)「大変ではありませんでしたか?」とモナシポフ氏に尋ねましたところ、涼しいお顔で「何も問題はありません」と言ってのけてくださいました。
実はこれまで拙作の演奏者からは散々苦情、批判、難癖、嫌み、罵倒を浴び続けてきましたので、半ばそれに慣れてしまい、初めて「何も問題ない」と聞かされると何故か申し訳ない気持ちになってしまいました。
また、この経験から如何に演奏家が駄々をこねても「世界レベル」の演奏家の手にかかれば「何も問題ない」こともあり、必要以上に卑屈にならなくてもよいことを学んだのでした。
どうも日本の演奏家、特に中堅、ベテランの一部の演奏家は比較的若い作曲家に難癖をつけたがる傾向(繰り返しますがあくまでも「一部」の演奏家です)にあるようです。
以前、チャイコフスキーの有名なバレエの「編曲」を手掛けた際、演奏家から「これでは演奏不可能だから書き直せ」と言われたことがありました。
その指摘を受けた箇所は原曲のまま、つまりチャイコフスキーが書いた通りで何も手を加えていなかったにもかかわらず・・・です。
モナシポフ氏の「異次元ぶり」はこれだけに留まりません。
オーケストラに於ける楽器のバランスは、例えば18世紀のモーツアルトの時代でしたらクラリネット奏者2名に対してヴィオラ奏者は10名になります。
つまりクラリネット1に対してヴィオラ5というのが標準的なバランスです。
単純計算でバランスを整えるためにはヴィオラ奏者はクラリネット奏者の「5倍」頑張ってもらわないとならないことになり、実際、日本での初演の際はクラリネットは少し「控えめに」ヴィオラはもっと「大きな音量で」とお願いする場面が多かったのですが、ここで同様の注文をする箇所は一つもありませんでした。
それどころかヴィオラの方がしばしばクラリネットの音をかき消してしまうことがあり、これには本当に驚かされました。
日本では絶対に有り得ないことで、ヴィオラがかくも豊かで幅広い響きを有するのかということを知り、ますますこの楽器の底知れぬ魅力にのめり込んでいくことになるのでした。
---来月更新予定の第10話に続きます---
(文/浅香満/日本・ロシア音楽家協会、日本作曲家協議会、日本音楽舞踊会議 各会員)
一覧に戻る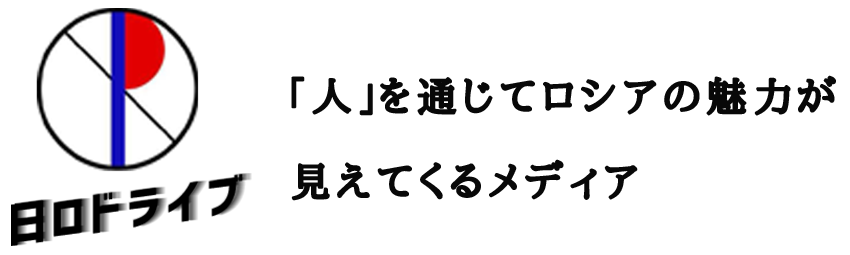

 2020.10.26
2020.10.26 
