ロシアを始めとした世界各地で開催される国際音楽祭に度々招かれるなど、世界を舞台に活躍されていらっしゃる音楽家・作曲家の浅香満さんのコラム「ロシア音楽裏話」第10話です。
前回までの連載記事はこちらから
(以下、浅香さんのコラムです)
.
.
.
.
.
ロシア、カザンで開催された「ヨーロッパ・アジア国際音楽祭」で拙作「クラリネット、ヴィオラ、ピアノのための三重奏曲」が披露されることになり、その本番前のリハーサルがカザン音楽院で行われ、「異次元」と言うべきヴィオラ奏者のK・モナシポフ氏の腕に度肝を抜かれましたが、国立交響楽団の首席クラリネット奏者でもあるA・グリファノフ氏の通常では有り得ないパフォーマンスにも大変驚かされました。
拙作の第4楽章にクラリネットの抒情的な旋律を数多く散りばめた「クラリネットの聴かせどころ」があるのですが、氏はそこを「完璧に」暗譜され、目を閉じて心を込めて演奏してくださいました。
その姿はまるで美しい「絵」のような一場面でありましたが、氏の複雑に絡み合った鳥の巣のような頭髪にちょうど窓ガラス越しに沈みゆく夕日が「後光」のように覆いかぶさり、恰も降臨した聖人のような雰囲気を醸し出していたのです。
その雰囲気を更に神々しいまでに高めたのが秀麗な弦楽器を思わせる表情豊かな「ビブラート」奏法でした。「ビブラート」というのは音をただ伸ばすのだけではなく絶妙に「揺れ」を加えることで表現力を高める奏法なのですが、その時、「ン!?!ビブラート??」と私の頭の中でクエスチョンマークが増殖していきました。
「クラリネットのビブラート」は、それまでの私には「有り得ない」世界であったからで、学生時代のレッスンでのある出来事が鮮明に甦ってきました。
皆さんは音大の作曲科の学生達がどのようなレッスン、授業を受けているかご存知でしょうか? 作曲を専攻する学生は「作曲実技」を中心に「作曲理論」といった作曲関連は勿論、他にも「管弦楽法」や「ソルフェージュ」等も履修しなければなりません。
「ソルフェージュ」というのは音楽の基礎訓練を指し、複雑で高度なリズム感覚の養成も含みますが、「聴音」が主体となっていました。
何しろ新入学すると何と「入学式」に先立って「聴音」の試験があり、能力別にクラス編成されるのですから。
歴史に名を残している偉大な作曲家はたった一度、曲を聴いただけで忽ちピアノ等で再現できたという伝説を持っていたりしますが、殆どの学生はそのような「天才」ではありませんので、数回に分けて(普通は4〜5回)音楽を聴いてそれを五線紙に書き取る訓練をします。
通常は作曲科の教員が段階的に難度が高くなるように課題曲を作曲して、ピアノを通して演奏し、学生がそれを書き取っていきます。
1クラス10数名程度の学生が毎週レッスンを受けるのですが、私たちのクラスを担当されたT・Y先生は新進気鋭の作曲家(本人がそう言っておりました)であり、「ソルフェージュ」としての目的は音楽的な基礎能力のアップですから、課題曲は音楽的な内容よりもどちらかと言えば「訓練」故、非音楽的で故意に難しく作られ、曲名も単に「課題曲A」「課題曲B」とされるのが普通なのにもかかわらず、この先生は全ての課題曲に詩的なタイトルを付けていました。
しかも風貌と反比例にロマンチストであった先生はこともあろうにタイトルは例外なく「愛の〇〇」と付けておりました。例えば「愛の萌芽」「愛の夜空」「愛の花」「愛の距離」といった感じで、中には「愛の果てに」という、意味深なものまでありました。
そしてソルフェージュの課題曲にもかかわらず「必要以上に」心を込めてピアノで弾かれるのです。「聴音」で求められるのは「書き取る」ことですから、大原則として指導者は同じテンポで「正確な」リズムで弾くことが求められるのですが、T・Y先生は自作の課題曲の「音楽的表現」を重視されたためか毎回弾くテンポが微妙に違い、しかも「ルバート」と言う表現法、つまり特定の音を楽譜に書いてある以上に伸ばしたり縮めたり、はたまた部分的にテンポを速めたり遅めたりなさり、およそ「ソルフェージュ」の本来の目的とは掛け離れた演奏となっておりました。
当然のことながら学生達から「そのような弾き方では音を書き取ることができない」という苦情が浴びせられるのですが、T・Y先生は全く聞く耳を持たず「音楽の命は楽譜の中にある情熱だ」と語ってテンポを「揺らした」演奏法を譲らず、先生の主張は確かに「正論」ではあるのですが、「ソルフェージュ」の「訓練」としては不向きであり毎回のレッスンがいつも険悪なムードになるのでした。
そのようなT・Y先生の大好物は「団子」です。
何故、学生がそれを知ったのかと言えば、音楽理論の講義で三和音の説明をする際、ちょうど音符を重ねた形が似ていたせいか「団子」に喩え、美しい三和音は串に刺された「美味しい三つの団子のようなもの」と力説したところから端を発し、やがて次第に話が逸れ、ついには団子についての蘊蓄に異様ともいえる熱弁を振るうこととなり、その蘊蓄は和音の説明の倍以上の時間に達していたからです。T・Y先生はとにかく熱いハートの持ち主で、どうでもいい内容でも最終的に「熱弁」になってしまうのでした。
作曲科の学生は年度末になると課題作品の作曲提出に追われ、またピアノ等の楽器の実技試験の練習も重なって睡眠不足に陥り、このような時はソルフェージュの基礎訓練は勘弁してほしい・・・という心境になりがちです。
そこでとある学生(もしかしたら私だったような気が・・・)が試しに授業の冒頭でT・Y先生に向かって「先生、U公園内に美味しいと評判の団子屋が開店したようですよ」と振ってみました。U公園は我々の大学のすぐ隣、正確に言えば大学もその公園の敷地内にあるのでした。
当初、T・Y先生はその学生の発言を無視して授業を始めようとピアノの前に座ったのですが、「団子」と言う魅惑の言葉は確実に先生の心に突き刺さり、まるで注射のように先生の体内に広がったようで、いつもは「心を込め」過ぎて書き取り不能なピアノを弾く先生の演奏が何となく上の空になったかと思えば、ついに堪えきれなくなったようで演奏を中断して突然立ち上がり(先生はしばしば何の前触れもなく「突然」立ち上がって周りを驚かせたものです)、「よし、その団子の味とやらを確かめに行くぞ!」と言うなり、授業時間中にもかかわらず10数名の学生を引き連れて大学を抜け出し、U公園内の団子屋に向かったのでした。実は件の学生は「新装開店」の看板を見たものの、そこの団子を食したことはなく「もし不味かったら・・・」と心配したようですが、結果は大当たり!でT・Y先生も大満足の様子でした。
美味しい団子の味に気を良くしたせいか、はたまた授業時間中に大学を抜け出した言い訳のためか、「これも謂わば生きた教育だ!」と言って団子を頬張りながら再び「突然」立ち上がり、作曲とは、芸術とは、音楽とは、教育とは等々、例によって「熱弁」を振るい始めました。
学生達はその美味しい団子(特に「鶯団子」は絶品でここの看板メニューとなっています)に夢中で誰一人聞いておらず(私もその時の先生の言葉は一言も思い出せません・・・)、先生の真横に座ってしまった不幸な学生が適当な相槌を打ってその場を凌いでいたのですが、先生の熱弁は完全に「ゾーン」に入ってしまったようで、もはや誰が聞いていようがいまいがお構いなしになり、暴走しだしました。
学生たちは皆「育ち盛り」であり、ソルフェージュの授業の時間帯がちょうど昼前であったこともあって、学生たちは次々に団子をお代わりし、その団子を盛っていた皿はまるで回転寿司の皿の如く先生の前に「山積み」にされていくのでした。すっかり「ゾーン」に入り込み自分の世界に陶酔しきっている先生には「山積みの皿」は全く眼中になく、おそらく学生達の姿も視界から消えてしまった様子で、おかげで真横に座った学生も上の空の適当な相槌から解放され、団子の味に専念しているようです。
なおも先生の熱弁の暴走が続く中、店の入口付近に座った学生が何やら腕時計を指し示しています。
見ると、ソルフェージュの授業時間はとっくに終了し、昼休み時間も残り僅かとなっており次の授業の開始時間も迫っておりました。
「お会計」が気になりましたが、先生の熱弁の終了を待っていては遅刻しそうです。
その熱弁はますます勢い付いてしまい、終了しそうな気配すら全くありません。
中には・・・と言うより殆どの学生が「確信犯」だったようで、「先生の前」に団子皿が山積みされていったことがそれを示しています。
頃合いを見計らって入り口付近にいた学生の合図で全員、一斉に脱兎のごとく店を出ました。
驚いたことに誰もいなくなっているのにもかかわらず、山積みされた皿の向こうで先生の熱弁は依然として続いているのでした。
T・Y先生は比較的若い世代故、「新進気鋭」であるとご自身で(本人以外は誰もそのように評しませんでしたが)語っていたのですが、作曲作品はともかく、そのユニークなソルフェージュの授業の展開方法は間違いなく「新進気鋭」に該当するかもしれません。
そのT・Y先生もかつてお世話になったこともある「大御所」の作曲家が「管弦楽法」を担当されているT・M先生です。
この先生は音楽業界のみならず多方面で広く知られている「有名人」であり、その名を高めたのはギネス記録を持ち、現在もなお続いているクラシック音楽TV番組の「初代司会者」であったことです。
因みにその音楽番組は先日の2月20日で「第2,700回」を迎えました。
週に1回しか放映されませんので、1年でせいぜい50回程度、10年でも500回程度となりますので、「2,700回」というのがいかにとてつもなく大きな数字であるかがわかることでしょう。
何と55年間に及ぶ世界最長の長寿番組で、T・M先生は司会だけではなく企画・構成もご自身でなさり、時には自ら指揮台に立ってオーケストラのタクトを振り、ジャズピアニストとしても活躍していたピアノの腕も披露されていました。
本業は勿論「作曲家」しかも世界的に注目を浴びている国際的な作曲家で、ハリウッド映画が威信をかけて制作した旧約聖書に基づく超大作の映画音楽を手掛けたことでも知られています。
なお、この映画の音楽は当初、ロシアの大作曲家イーゴリ・ストラビンスキーが務めることになっていたようなのですが、諸事情によりT・M先生に白羽の矢が立ったのでした。
また作曲家と言う人種は私も含めて「口下手」な者が多く、先程のT・Y先生もそうだったのですが、何を言っているのかよくわからず、発言内容が意味不明、不可解、一貫性に欠ける、矛盾だらけ、回り諄い、意味なく長い(このコラムの読者の皆さんでしたら容易に想像できるでしょうね)というのが珍しくない中、T・M先生の司会は実に軽妙洒脱で言語も明瞭、内容は的確であったことから、中には司会業のプロであると勘違いした視聴者も多かったようです。
企画も先生ならではの斬新な内容が多く、例えば「正調蝶々夫人」なる珍妙なものまでありました。
歌劇「蝶々夫人」はイタリアのオペラ作曲家のジャコモ・プッチーニが手掛けた最高傑作の一つですが、日本の長崎が舞台になっているにもかかわらず全てのセリフが「イタリア語」となっています。
それに異を唱え「日本語」に翻訳して演じられることも日本ではたまにあるのですが、先生曰く、「長崎が舞台なのに『標準語』もおかしい」とのことで、何と全編を「長崎弁」で上演したことがありました。
これには出演した世界的オペラ歌手達もさすがに面食らってしまい、もとよりイタリア語の歌詞に絶妙にマッチするように美しく作曲されていたメロディーに彩られた名作が、まるで吉本新喜劇のような空間となってしまい、ステージも客席も笑いを堪えるのに必死だったことがありました。
実は、この番組の収録は「隔週の金曜日の午後」に渋谷公会堂で一度に「2回分」が行われるのですが、T・M先生担当の「管弦楽法」の大学での授業、レッスンも同じ金曜日の午後に設定されているのでした。
つまり、一週おきに自動的に「休講」となる訳です。
さらに当時のT・M先生の人気は絶大で、コーヒー、車のCM出演だけでなく、何を血迷われたのか化粧品のCMにまで進出されていました。
いつぞやは地下鉄駅構内の壁や柱の一面に化粧品を手に微笑む先生のお顔のドアップのポスターが連続して何枚も貼られていたことがあり、弟子ながら少し気恥しい思いをしたこともありました。
また誰にも忖度することなくTVの司会同様に自分の主張を歯に衣着せることなく披露する「毒舌家」としても知られ、右翼の活動もなさる「超多忙」のスケジュールで、ある年は一年間に僅か「2回」しか授業、レッスンがなかったこともありました。
現在私が所属する大学では前期(春学期)、後期(秋学期)共に「15回」の講義が義務付けられており、もし自分の都合で休講した場合はその学期内に必ず「補講」しなければならない規則になっています。
昔はそのような規定はありませんでしたので、T・M先生のような偉大な方の「講義を犠牲」にする「偉業」がこのような規定を齎せたものと推察されます。
---来月更新予定の第11話に続きます---
(文/浅香満/日本・ロシア音楽家協会、日本作曲家協議会、日本音楽舞踊会議 各会員)
一覧に戻る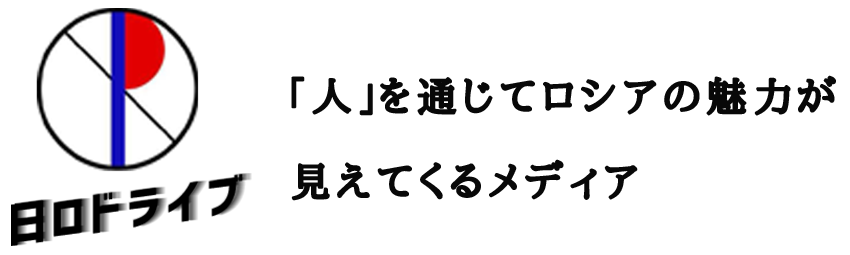

 2020.07.30
2020.07.30 
